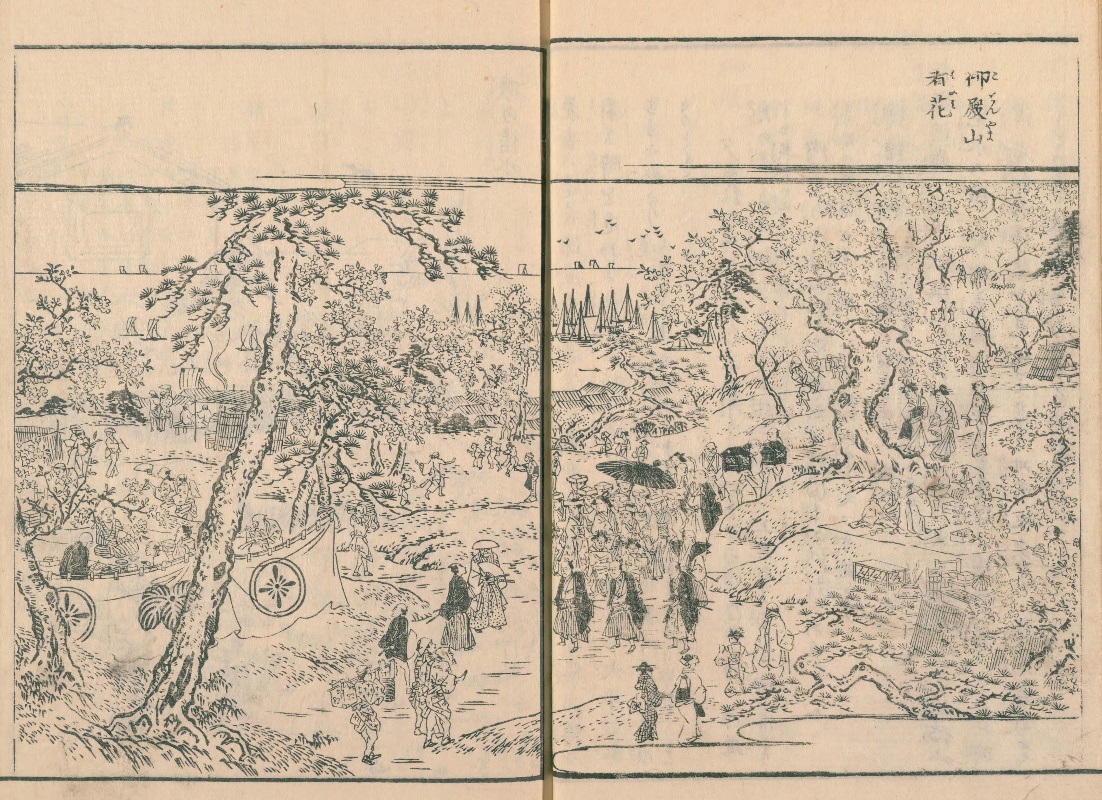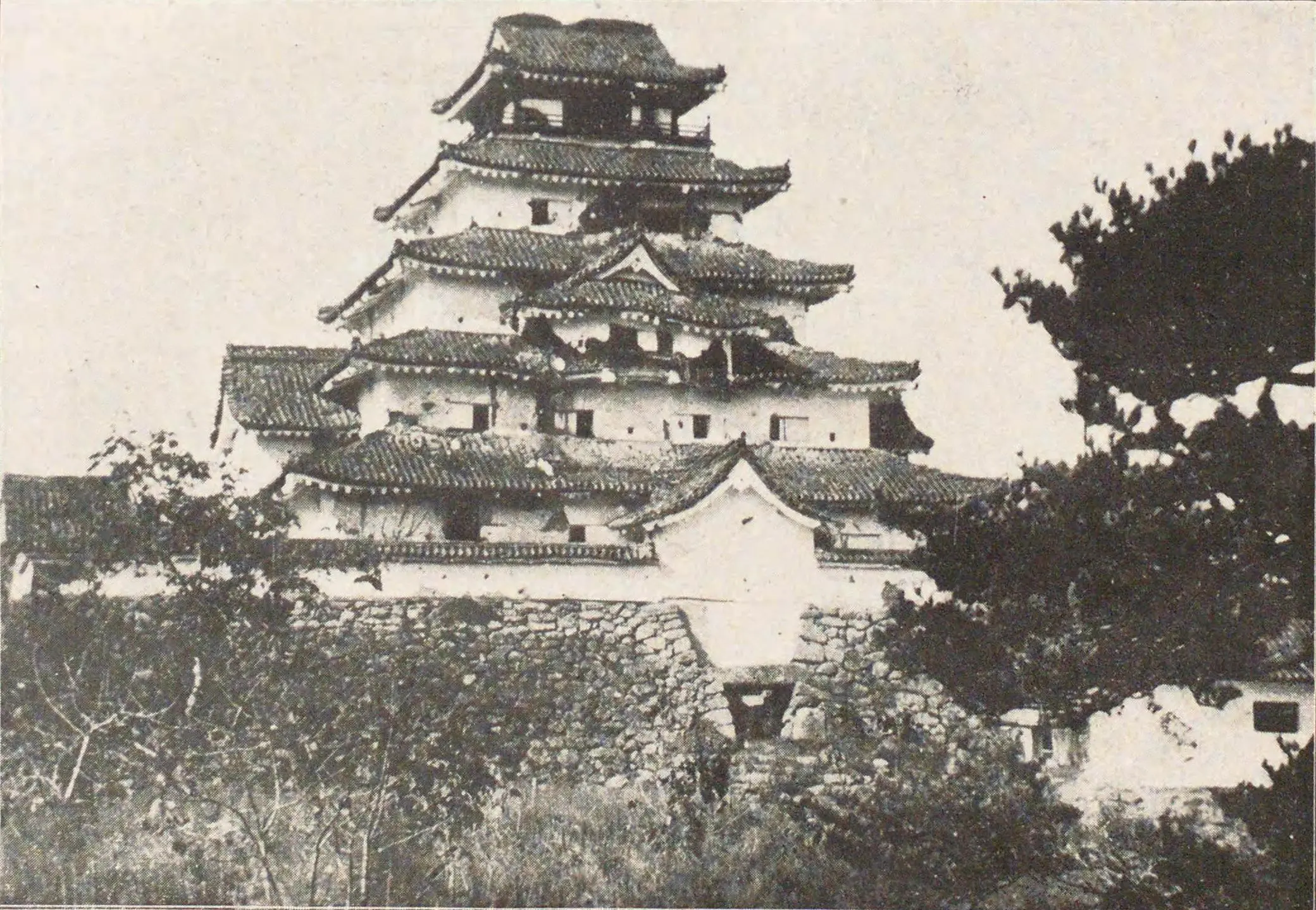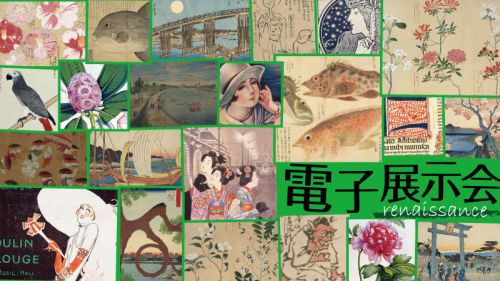北海道のスキー場(明治時代末~昭和初期)
日本の最北端に位置する北海道は、年間を通じて気温が低く、冬には雪が一面を覆う。そのような冬も楽しめる遊びの一つとして、人々に親しまれてきたのが「スキー」である。
明治44(1911)年にオーストリア=ハンガリー帝国の軍人テオドール・フォン・レルヒがスキーの指導を行った新潟県上越市(高田)は「日本スキー発祥の地」として知られている。もっとも、それ以前にも日本でスキーが紹介された記録はある。江戸時代に樺太を探検した間宮林蔵の『北蝦夷図説』には、スキーに似た道具が描かれている。また、明治35(1902)年に冬の八甲田山で発生した遭難事件を受け、神戸のスウェーデン・ノルウェー総領事ペーター・オッテセンがノルウェーからスキーを取り寄せたという(1)。
北海道においては、明治41(1908)年に東北帝国大学農科大学(北海道大学の前身)のドイツ語講師に着任したハンス・コラーが、学生たちにスキーを紹介した逸話が伝わっている(2)。コラー自身にスキーの経験はなかったが、授業でスキーを取り上げたことで学生たちに懇願され、海外から道具を取り寄せた。学生たちは札幌の三角山の麓で滑走を試みたという。
日本スキー発達史
写真遊覧
また、高田でスキーを指導したレルヒは、明治45(1912)年旭川の第七師団に赴任し、ここでも軍人たちにスキーを教えた。同年には、高田でスキーを学んだ小樽高等商業学校(小樽商科大学の前身)の苫米地英俊が学校前の坂道で練習会を開き、市民へスキーを伝えている(3)。
大正11(1922)年には三角山に国内初の固定スキージャンプ台「シルバーシャンツェ」が着工し、大正12(1923)年には小樽で第1回全日本スキー選手権大会が開催された。
昭和3(1928)年には秩父宮が北海道を訪れ、札幌近郊やニセコでスキーを楽しんだ。秩父宮は、将来日本で冬季オリンピックを開くとすれば札幌以外にない、と助言したという(4)。その後、昭和7(1932)年、札幌に60メートル級の大型ジャンプ台が開場し、「大倉シャンツェ」と名づけられた。
しかしながら、昭和15(1940)年に予定されていた札幌オリンピックは、日本が開催権を返上したため幻のオリンピックとなってしまう(5)。北海道でオリンピックが実現するのは、戦後の昭和47(1972)年、第11回冬季オリンピックまで待たねばならなかった。
現在、北海道でスキーを楽しむのは日本人だけではない。スキーに適したサラサラとした粉雪は「パウダースノー」とも称され、ニセコなどがスキーの名所として国際的な観光地となっている。
昭和初期の北海道のスキー場
注
参考文献
- 北海道大学スキー部創立100周年記念史編集委員会 編, "北海道大学スキー部創立100周年記念史" (北海道大学スキー部OB会 2012)
- 前田克己 著, "スキー発達史 : 後志のスキー 増補改訂版" (倶知安郷土研究会 2022)
- 中川喜直 著, "もうひとつのスキー発祥の地 : おたる地獄坂" (小樽商科大学出版会 2011)
- 栗林薫 編著, "北海道一般スキー八十年の歩み" (広告の岩泉 1991)
- 長岡忠一 著, "日本スキー事始め : レルヒと長岡外史将軍との出会い" (ベースボール・マガジン社 1989)
- 佐藤徹雄 著, "北海道のスキーづくり" (市立名寄図書館 1983)
- 大野精七 著, "北海道のスキーとともに" (サンケイ総合印刷 (印刷) 1971)
- 北海道総務部知事室道民課 編, "北海道開発功労賞受賞に輝く人々 昭和45年" (北海道 1971)