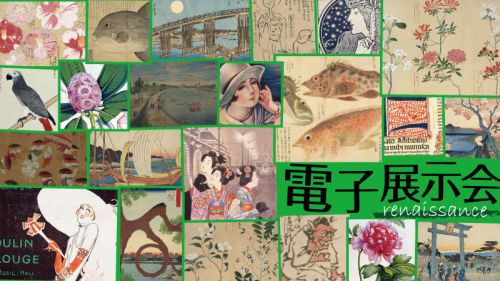師走
和風月名

事始め
師走に入ると1年間の汚れを落として家を清め、新年を迎える仕度を始めます。事始めと呼ばれ、武家・町家を問わず煤払いを行い、一家総出で行う賑やかな行事でした。掃除も単なる掃除と異なり、一年の厄を祓い、年神を迎える準備をする儀式でした。煤払いが済むと、商家などでは祝儀や酒肴を振る舞いました。
歳の市(年の市)
暮になると各地で正月用品を売るための市がたちました。慌ただしい年の瀬の「歳の市」は、浅草の市が江戸で一番の規模でした。市ではしめ飾りなどの飾り物をはじめ、お節料理・羽子板・凧などの遊び道具、箒・暦といった多彩な商品が並び、多くの人々が正月用に買い求めに集まりました。
餅つき
餅つきは正月前の神聖な行事とされ、米を蒸す蒸籠や餅をつく臼にはしめ縄が張られ、臼の下には塩で清めた藁が敷かれました。またつく日も29日は苦餅、大晦日は一夜餅として避けられました。
雪見
1年で最も日が短くなる冬至には、寒さが一段と厳しくなり雪のシーズンとなります。「雪月花」は日本人の美意識を形作る象徴として愛されてきましたが、中でも白一色の世界に対する思いは深かったようです。江戸の町が雪に覆われると、名所に人々は足を運び雪見を楽しみました。隅田川の堤・三囲・長命寺・不忍池・上野寛永寺などは名所として有名です。
こちらもご覧ください
和風月名